アクティブラーニング あくてぃぶらーにんぐ
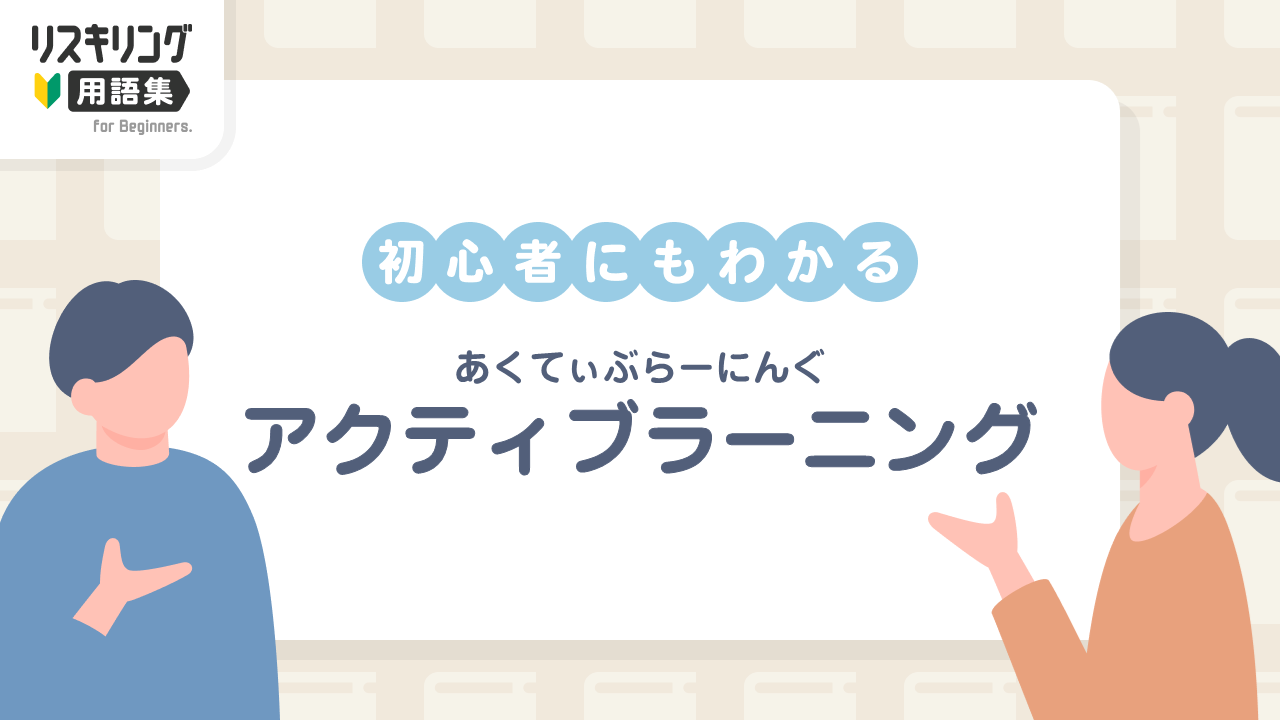
近年、急速な技術革新やビジネス環境の変化に伴い、企業にとって「リスキリング」の重要性が高まっています。リスキリングとは、従業員の既存のスキルを更新し、新しい能力を身につけさせることで、変化する職場のニーズに適応させるだけでなく、新しい業務や職業にも対応できるようにする取り組みです。
本用語集では「アクティブラーニング」に関連する概念を初心者にもわかりやすく解説していきます。
目次
「アクティブラーニング」をひとことでいうと?
アクティブラーニングとは、教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学習者が主体的・能動的に学びに参加する教育手法を指します。
アクティブラーニングの基本概念
「アクティブ(active:能動的・活動的)」と「ラーニング(learning:学習)」を組み合わせた言葉であるアクティブラーニングは、学習者が単に講義を聴くだけの受動的な学習スタイルから脱却し、自ら考え、議論し、実践する能動的な学習プロセスを重視します。この学習方法では、教員は知識の一方的な伝達者ではなく、学習者の主体的な学びを支援するファシリテーター【1】としての役割を担います。さらに、アクティブラーニングでは、学習者同士の協働学習を重視し、他者との対話や協力を通じて、多様な視点や考え方に触れることができます。また、学習プロセスや成果を振り返ることで、学びの質を高め、実践的なスキルの開発にもつながります。
アクティブラーニングの歴史と発展
アクティブラーニングの概念は、1980年代にアメリカの高等教育で注目され始め、ハーバード大学やMITなど大学でのグループディスカッションやプロジェクトベースの学習方法として広く採用されました。
日本では、2012年の中央教育審議会答申で「アクティブ・ラーニング」という用語が使用されましたが、2017年に文部科学省から告示された学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」という表現に変更されました。この変更は、単なる活動や技法の表面的な導入ではなく、学習の質的転換を重視する意図から行われました。現在は初等教育から高等教育まで、この新しい学びの考え方が広く実践されています。
ビジネス業界におけるアクティブラーニングの活用
企業研修の分野でも、2015年頃から従来の座学中心の研修からアクティブラーニングの考え方を取り入れた研修への転換が進み、特に2020年以降、リモートワークの普及とデジタルトランスフォーメーション(DX)【2】の加速により、従来の座学中心の研修スタイルから、より実践的な学習方法への移行が進んでいます。
教育現場では「主体的・対話的で深い学び」という表現が採用されていますが、ビジネス業界では、アクティブラーニングはオンラインでの双方向的な学習環境の構築や、創造的な問題解決手法の開発、さらには組織全体の変革ツールとしても活用されており、特にグローバル企業との協働では国際的に通用する「Active Learning」という表現が定着しています。
アクティブラーニングが注目されている背景
正解のない時代への対応
VUCA時代【3】と呼ばれる現代では、市場環境や技術革新の速度が加速し、既存の知識や経験だけでは解決できない複雑な問題が日々増加しています。このような状況下では、固定観念にとらわれることなく創造的に考え、多様な視点を取り入れながら、柔軟かつ効果的な解決策を見出す力が、かつてないほど強く求められています。
リスキリングの需要急増
技術革新やビジネスモデルの急速な変化に伴い、従来の知識やスキルが急速に陳腐化する状況が生まれています。そのため、社員が定期的かつ主体的に新しいスキルを学び直すリスキリング【4】の必要性が著しく高まっており、短期間で効果的な学習成果を上げられる実践的な学習方法が強く求められています。特にデジタル技術の進展により、従来の業務プロセスや必要とされる職能が大きく変化している現状では、組織全体での継続的な学び直しの仕組みづくりが重要な経営課題となっています。
eラーニング技術の発展と普及
デジタルプラットフォームや学習管理システム(LMS)【5】の急速な進化により、時間や場所の制約を超えた双方向的な学習環境が技術的に実現可能となっています。さらに、クラウドベースのツールやビデオ会議システムの普及により、リアルタイムでの対話やグループワーク、ディスカッションなども容易に実施できるようになり、従来は対面でしか実現できなかったさまざまな形式のアクティブラーニングが、オンライン環境でも効果的に展開できるようになっています。
企業研修におすすめのアクティブラーニング手法
アクティブラーニングには多様な手法があります。とくに、企業研修に適している代表的な手法をその特徴と共に紹介します。これらは、短期間で具体的な成果を出せること、実務への応用が容易であること、そして参加者の主体性を引き出せることが特徴です。
グループディスカッション
概要:共通のテーマについて少人数で意見を出し合い、対話を通して理解を深める学習法。
企業研修に適している理由:
日常業務では立場や役職によって意見交換が制限される場面もありますが、ディスカッションの場では自由な発言が許されます。その結果、異なる視点や考えに触れることで認知の幅が広がり、多面的な問題解決力が育まれます。また、チーム内の関係性構築にもつながり、コミュニケーションの活性化が期待できます。
ケーススタディ
概要: 実際のビジネス事例を用いて、課題分析と解決策の立案を行う手法。
企業研修に適している理由:
理論やフレームワークを「実際の状況に当てはめて考える力」が求められるため、単なる知識習得に留まらず、応用力や判断力が鍛えられます。自社の業務に近い事例を扱うことで、学んだ内容が日々の業務と直結しやすく、職場に戻ったあとも定着しやすいのが特徴です。
ロールプレイ
概要: 上司や顧客など、異なる立場になりきって模擬対応を行う練習法。
企業研修に適している理由:
マニュアルや座学では学べない「反応への即応力」や「非言語のコミュニケーション」が体得できるため、実践的な力を短時間で伸ばせます。営業や接客、管理職向けの対応スキルなど、リアルな場面を想定した反復練習が可能で、フィードバックも取り入れやすい手法です。
ピアラーニング
概要:学習者同士で教え合いながら学ぶスタイル。
企業研修に適している理由:
「教える側」になることで、自分の理解のあいまいさに気づき、学びが深まります。また、上司・部下の関係を超えて知識を共有する文化が生まれやすく、チーム内での心理的安全性やエンゲージメント【6】の向上やリスキリングやOJT【7】にも活用できます。
プロジェクト型学習(PBL)
概要:実際の課題解決を目的としたプロジェクトを進めながら学ぶ手法。
企業研修に適している理由:
成果を出すことを前提に学ぶため、抽象的な学習に留まらず、行動につながるアウトプットが促進されます。チームで協働する中でリーダーシップや折衝力も磨かれ、企業が求める「現場で使える力」が養われます。特に若手の育成やDX推進研修などに適しています。
概要:まず個人で考え、次にペアで共有し、最後に全体で発表する3段階の学習法。
企業研修に適している理由:
内向的な社員でも自分の考えを整理する時間があり、いきなり発表するプレッシャーが軽減されるため、安心して参加できます。段階を踏んで意見を深めていける構造が、短時間でも「自分ごと」の学習を可能にし、理解と納得が伴った行動変容につながります。
ジグソー法
概要:チームメンバーが情報を分担して学び、互いに教え合いながら全体像を構築する手法。
企業研修に適している理由:
一人ひとりが「必要なパーツを担う」構造なので、受け身にならず、責任感をもって参加する姿勢が育ちます。分業や情報共有、相互理解が不可欠な企業現場において、部門間連携のトレーニングとしても効果的です。グループ単位での研修にも最適です。
LTD(Learning Through Discussion)
概要:事前学習で得た知識をもとに、少人数での話し合いを通じて理解を深める「話し合い学習」。
企業研修に適している理由:
予習と対話による構造的な学習プロセスを通じて、論理的思考力・傾聴力・発信力が高まり、会議や商談などの場面でも活かせる実践力が身につきます。主体性や対話力が求められる現代のビジネス環境に適しています。
フィールドメソッド
概要:職場や顧客現場に出て観察やインタビューを通じて課題を発見し、分析・提案を行う学習法。
企業研修に適している理由:
デスク上の理論だけでなく、現場に根ざした課題認識と解決力を養うことができます。とくにサービス業や製造業では、現場のリアリティを体感することで本質的な気づきが得られ、業務改善や新規提案につなげやすくなります。
経営者・人事担当者のための「アクティブラーニング」Q&A
Q1:アクティブラーニングはすべての研修に向いていますか?
A:アクティブラーニングは、問題解決能力やチームワークの向上、実践的なスキルの習得が必要な場面で特に効果的です。一方で、基礎的な知識の習得や専門的な理論の理解が主な目的となる場面では、従来の講義形式の方が効率的です。また、時間的制約が厳しい場合や、参加者の人数が多い場合にも、講義形式の方が適切な選択となることがあります。
Q2:従来の研修と比べてコストは高くなりますか?
A: 初期投資は従来型の研修と比較して大きくなる傾向があります。これは、教材の開発、ファシリテーターの育成、必要な機材やツールの準備などに費用がかかるためです。しかし、長期的な視点で見ると、学習効果の向上により知識の定着率が高まり、再研修の必要性が減少し、さらに実践的なスキル習得により業務効率も向上するため、人材育成の総コストは削減できる可能性があります。
Q3:ファシリテーターは社内でも育てられますか?
A:可能です。具体的には、まず基礎的なファシリテーションスキルの研修から始め、次に実践的なワークショップでの経験を積み、最後にベテランファシリテーターの下でメンターシップを受けるという段階的なアプローチが推奨されます。また、熟練ファシリテーターをロールモデルとして設定し、その実践方法や心構えを学ぶ機会を設けることで、より効果的な育成が可能となります。
まとめ
アクティブラーニングは、変化の激しい現代のビジネス環境において不可欠な人材育成手法として注目を集めています。従来型の一方向的な知識伝達から脱却し、学習者が主体的に参加する新しい学びのスタイルへと転換することで、実践的なスキルの効果的な開発が可能となります。さらに、アクティブラーニングは、組織全体の学習文化を活性化し、メンバー間の相互学習を促進する効果も期待できます。デジタル技術との融合により、時間や場所の制約を超えた柔軟な学習環境の構築が可能となり、さらなる発展が期待される分野です。
関連用語
【1】ファシリテーター(Facilitator)
グループ活動の中立的な進行役として、メンバー間の対話を促進し、意見を引き出しながら建設的な議論を促進する役割を担う人。
【2】デジタルトランスフォーメーション(DX)
デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや組織文化を根本的に変革し、顧客価値や競争力を高めるプロセス。単なるIT化ではなく、デジタル技術を核とした経営戦略の変革を意味する。
【3】VUCA時代
Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉で、不確実で予測困難な時代を指す。
【4】リスキリング(Reskilling)
従業員に新しいスキル、能力を習得させることで、職場の変化や新たな業務にも対応できるようにする取り組み。
【5】学習管理システム(LMS:Learning Management System)
従業員の教育・研修を効率的に管理・運営するためのシステム。eラーニングコンテンツの提供、学習進捗の追跡、成果の評価など、組織の学習活動を包括的に支援する。
【6】エンゲージメント (Engagement)(リスキリング用語集⑧)
従業員の仕事や組織に対する熱意、関与度を表す概念。生産性向上や離職率低下につながり、組織の成長に重要な要素。
【7】OJT(On-the-Job Training)
実際の職場で日常の業務を通じて行われる教育訓練のこと。従業員が実践的なスキルや知識を習得するために、実際の業務環境の中で上司や先輩から指導を受けながら学ぶ方法。